

さまざまな調理で食されるさつまいも。江戸時代初期までは九州南部だけでつくられ食べられていたと伝わります。全国的に知られるようになったのは江戸時代中期。栽培の普及に尽力したのが芋神様や甘藷先生などと言われる青木昆陽です。
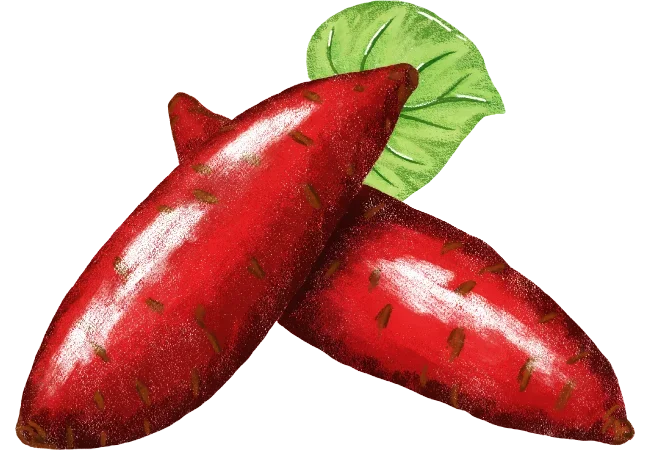
救荒作物としての有用性
江戸に生まれた青木昆陽は蘭学者として知識を深め、幕臣に取り立てられます。当時の幕府が抱えていた大きな課題は、数年前に起こった江戸三大飢饉の一つ享保の大飢饉です。1万人以上が餓死し、200万人以上が飢えに苦しんでおり、将軍・徳川吉宗や幕臣はその対応や対策に苦慮していました。青木昆陽は書物で知った甘藷(さつまいも)に着目。救荒食物としての有用性や栽培法などをまとめた「蕃藷考(ばんしょこう)」という小冊子を著し将軍に献上します。翌年には青木昆陽は幕府の許しを得て、現在の千葉市幕張の他、小石川薬園(現・文京区)・九十九里でさつまいもを試作して一定の成果を収めました。
飢饉から人々の命を救う
これを契機に、さつまいもは日常食として江戸庶民の暮らしを支える作物になり、幕張周辺でも栽培量が増えていきます。痩せた土地でも育つさつまいもの全国的な普及は、この後に起こる天明、天保の大飢饉でも米の不作を大いに補い、多くの人々の命を救ったと言われます。幕張周辺の村民は、多数の命が救われたこと、芋苗の販売による収益への感謝などから、試作地に社殿を建て青木昆陽の霊を祀るようになりました。明治・大正時代には品種や栽培の改良が進み、さつまいもを原料とするデンプン製造業が幕張周辺では盛んになりました。昭和初期の戦中・戦後の食糧難の時代には、米の代用食と言われ多くの人を飢えから救います。さつまいもを広めた青木昆陽の評価が高まる中、幕張の試作地跡は戦後しばらくして千葉県指定史跡となりました。現在でも千葉県は収穫量や作付面積で全国3位(2022年)で、国内有数のさつまいも産地です。




