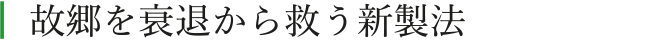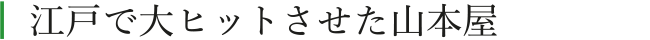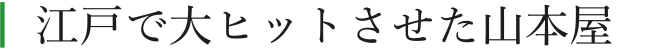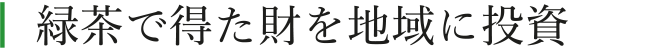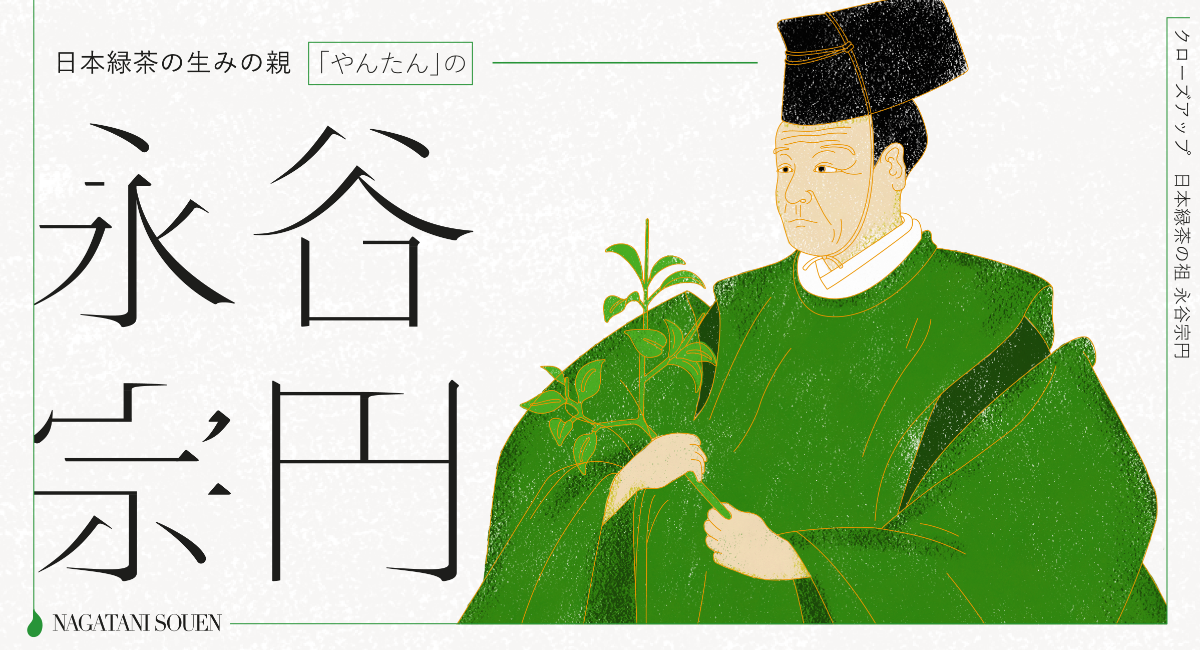

現在、日本で飲まれるお茶のうち約7割は緑茶です。日本で緑茶が一般化し始めたのは江戸時代中期のこと。宇治田原町にある小さな村の庄屋・永谷宗円(ながたにそうえん)が、苦境に立つ村の未来を救うため、15年もの歳月をかけて日本緑茶の製法を考案。江戸での大ヒットを経て、全国的に緑茶が広がりました。
江戸時代初期、飲まれていたお茶は大きく分けて2つです。一つは碾茶(てんちゃ)で臨済宗の開祖・栄西が、鎌倉時代に中国から伝えた製法を基にしています。てん茶を細かく挽くと抹茶になり、高級な緑色の抹茶は上流階級の茶の湯として日本全国に浸透しました。もう一つは、お茶の名の通り「茶色」の煎茶です。釜炒り茶や日干番茶の系統に属する製法で、庶民が口にする粗末なお茶でした。


永谷宗円は1680年に、現在の京都府にある宇治田原町の湯屋谷(ゆやだに)で、名字帯刀を許された庄屋の家に生まれました。湯屋谷には谷を「たん」と言う方言があり、地元の人は故郷を「やんたん」と愛称で呼びます。今も昔も湯屋谷は山間の小さな集落で、古くからお茶の栽培が盛んな土地でした。ただし、高級なてん茶栽培(覆い下栽培)は宇治地方の中でも特定の御茶師にしか許されておらず、湯屋谷ではもっぱら茶色の煎茶を露天栽培していたのです。


宗円が庄屋を務める頃、庶民用のお茶の売れ行きが落ち込んでおり、湯屋谷には「これでは村の先行きが厳しくなる」という危機感がありました。そこで宗円は、法に触れずに露天栽培でも優れた煎茶をつくれないかと43歳の時から研究を始めたのです。近郊の宇治で行われるてん茶製法を参考に、試行錯誤を繰り返しながら15年もの歳月を費やし、新しい製法を完成させました。色鮮やかな濃い緑色の茶葉にお湯を注ぐと、澄んだ黄緑色のお茶が器に広がり、その味わいは適度な渋み、苦味、甘みが調和。後にこの製法は特徴から「青製煎茶」や、地域の名前から「宇治製煎茶」と呼ばれるようになりました。

宗円は完成させた煎茶を持って江戸へ赴き、茶商らに売り込みました。しかし「煎茶は茶色いもの」という常識から、ことごとく商談を断られます。それでも諦めずに4軒目に飛び込んだ茶商山本屋で、緑色の煎茶の味を当主が絶賛。宗円が持参した分を全て購入し、さらに来年の買取も約束したのです。山本屋が「天下一」と名付けて販売すると、江戸町民の間で爆発的な人気を得ました。山本屋の日記には「江戸市民が宇治茶を愛用するようになった」と記されています。山本屋の家名は宗円の緑茶で大いに上昇しました。ちなみに山本屋は後に社名を「株式会社 山本山」に改名。現在も湯屋谷と親密な交流を続けています。

江戸で話題となった後、宗円は自ら考案した「青製煎茶」の製法を独占することなく、近隣の人々に惜しみなく伝授したそうです。そのおかげで宇治での生産量が高まり、宇治製の煎茶は明治初頭までにはほぼ全国的に普及するようになりました。日本緑茶の発明で多くの富を得た宗円は、湯屋谷や近郊の村々で湿田の排水工事を数多く手掛けます。次第に村民からは「干田大明神(かんだだいみょうじん)」と呼ばれるようになりました。宗円は98歳という高齢でその生涯を閉じます。宗円が永眠した日は茶摘みで村中が賑わう5月中旬で、「青々とした茶畑に見送られた」と地元の人は語ります。現在は茶宗明神(ちゃそうみょうじん)として湯屋谷にある茶宗明神社に祀られています。


宇治茶の主要産地・宇治田原町のほぼ中央に位置する集落。山間の細い谷筋に形成された小さな集落の中に、大きな茶問屋や茶農家が軒を連ねる町並みが続きます。日本遺産「日本茶800年の歴史散歩」の構成文化財に「湯屋谷の茶畑、茶農家、茶問屋の街並み」として登録されています。

昭和35年に再建された宗円の生家。以前は製茶小屋や倉庫を備えていたと伝わります。内部には製茶に使われた焙炉(ほいろ)跡が保存。映像でお茶の製法や宗円の足跡を知ることができます。ちなみに「お茶漬け海苔」で有名な永谷園は、宗円の子孫が創業しました。